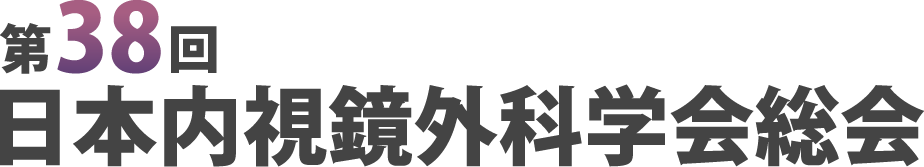演題募集
演題募集期間
| 2025年4月16日(水)正午~ | |
|
演題募集を締切りました。 |
演題登録
以下の「演題登録はこちら」ボタンから演題登録画面にお進みください。
非会員(現時点で筆頭演者が会員でない方、メディカルスタッフ・工学系研究者・初期研修医)
筆頭演者ならびに共同演者は全て会員に限りますので、未入会の場合は演題登録後、必ず入会申込を行ってください。
(メディカルスタッフ・工学系研究者・初期研修医・外国籍の方を除く)
会員情報に関するお問い合わせ
日本内視鏡外科学会 事務局
info-jses@convention.co.jp
応募資格
JSES会員専用ページから演題を登録いただくことになりました。
筆頭演者ならびに共同演者は全て会員に限ります。
(メディカルスタッフ・工学系研究者・初期研修医・外国籍の方を除く)
筆頭演者ならびに共同演者については、演題登録時に「会員番号」が必要となります(10ケタ)。
会員の方は、「会員番号」を事前にご確認のうえ演題登録を行ってください。
共同演者の会員番号と氏名のカナも登録に必要です。
必ず、事前にお手元にご用意ください。
共同演者の会員番号が不明な場合は、個人情報に該当しますので原則共同演者ご本人に確認ください。
共同演者の同意がある場合に限り事務局にてお調べいたしますので、下記メールアドレスまでメールにてお問い合わせください。
お問い合わせの際、必ずメールに、共同演者の「氏名」「氏名カナ」「所属先名」「生年月日」ならびに「共同演者より事務局からの会員番号のお知らせについて同意を得ている旨」を記載してください。
JSES事務局 E-mail:info-jses@convention.co.jp
入会については下記学会のホームページより、ご申請ください。
入会申請から本登録までには1週間程度かかりますので、お時間に余裕をもってご入会いただきますようお願いいたします。
なお、メディカルスタッフ・工学系研究者・初期研修医・外国籍の方は、職種にて必ず医師以外を選択ください。
公募について
第38回総会では、一部の主題演題及び一般演題のカテゴリーにおいて皆さまより演題を募集いたします。
演題の採否、発表形式、発表分野につきましては、会長にご一任ください。
「主題演題」希望の場合でも、一般演題での採用となる場合もございます。また、「一般演題」希望の場合でも「主題演題」での採用となる事もございます。
現地開催を想定しております。リモート登壇の想定はございません。
【研修医・基本領域専攻医・医学生】について
本総会において、将来の医学・医療を担う若手医師の学術的成長を目的として、
研修医、基本領域専攻医、医学生による演題応募を奨励しております。
発表された研修医・基本領域専攻医・医学生には、
その意欲と努力を称えるべく、表彰状を授与いたします。
多くの若手医師にとって、学会発表が貴重な経験となることを願っております。
皆様の積極的なご応募をお待ちしております。
文字数制限など
| 演題名 | : | 全角50文字以内
英語の場合は半角100文字以内 |
| 抄録本文 | : | 全角550文字以内
英語の場合は半角1,100文字以内 |
| 登録可能な演者数 | : | 筆頭演者を含め15名以内 |
| 登録可能な所属機関 | : | 10施設以内 |
応募締切直前は回線が大変混み合うことが予想されますのでお早めにご登録ください。
抄録本文はご登録をいただきました通りでの掲載となりますので、誤字脱字等ご注意ください。
応募カテゴリー(一般演題)
発表形式は「口演」もしくは「ミニオーラル」をご選択ください。
なお、演題の採否及び発表形式の決定は会長にご一任ください。
部門(必須)
| 1 | 研修医・基本領域専攻医・医学生 | 21 | 小腸 |
|---|---|---|---|
| 2 | メディカルスタッフ/看護師 (安全管理・麻酔補助・教育・その他) |
22 | 結腸・直腸・肛門良性 |
| 3 | メディカルスタッフ/CE (安全管理、保守管理、その他) |
23 | 結腸・直腸・肛門悪性 |
| 4 | 手術機器・器具 | 24 | 肝臓 |
| 5 | 救急医療 | 25 | 胆嚢・総胆管 |
| 6 | 移植医療 | 26 | 膵臓 |
| 7 | 脳・神経 | 27 | 脾臓 |
| 8 | 耳鼻咽喉科頭頸部外科 | 28 | ヘルニア・腹壁・腹膜 |
| 9 | 乳腺 | 29 | 肥満・代謝 |
| 10 | 呼吸器良性・気胸 | 30 | 小児外科 |
| 11 | 呼吸器悪性 | 31 | 副腎 |
| 12 | 気道 | 32 | 腎臓・尿管 |
| 13 | 縦隔 | 33 | 膀胱・前立腺 |
| 14 | 胸部交感神経幹 | 34 | その他の泌尿器科領域 |
| 15 | 心臓・大血管 | 35 | 子宮 |
| 16 | 末梢血管 | 36 | 卵巣 |
| 17 | 食道良性 | 37 | その他の婦人科領域 |
| 18 | 食道悪性 | 38 | 整形外科 |
| 19 | 胃・十二指腸良性 | 39 | 形成外科 |
| 20 | 胃・十二指腸悪性 | 40 | その他 |
内容(必須)
| 1 | 外科解剖 | 16 | 教育 |
|---|---|---|---|
| 2 | 適応 | 17 | 技術認定 |
| 3 | 治療成績 | 18 | Day Surgery |
| 4 | 手術手技 | 19 | クリニカルパス |
| 5 | 偶発症・合併症 | 20 | インフォームド・コンセント |
| 6 | ロボット支援手術 | 21 | リスクマネージメント |
| 7 | 内視鏡外科手術室関連 | 22 | 医療経済 |
| 8 | バーチャルリアリティ・シミュレーション | 23 | ダイバーシティ |
| 9 | ナビゲーション | 24 | AI(人工知能) |
| 10 | エネルギーデバイス | 25 | 遠隔医療 |
| 11 | 医療機器管理 | 26 | ビッグデータ・NCD |
| 12 | 医療材料 | 27 | Greenhouse Gas/CO2削減、環境問題 |
| 13 | Reduced Port Surgery / Needlescopic Surgery |
28 | 新型コロナ・感染症 |
| 14 | ヘルニア | 29 | スコープオペレーター |
| 15 | NOTES | 30 | その他 |
| 上部消化管領域 | セッション形式 |
|---|---|
胃癌に対するロボット支援下手術は腹腔鏡下手術を凌駕するか?セッション趣旨はこちら 胃癌に対する手術において、腹腔鏡手術は広く普及しているが、ロボット支援下手術はその精密な操作性と三次元視野により、新たな選択肢を提供している。ロボット支援手術が腹腔鏡手術を凌駕するかについては、手術時間、合併症率、長期予後、患者満足度などの観点で議論が続いている。本シンポジウムでは、両アプローチ法の比較、エビデンスに基づく成果、さらには今後の技術進展について共有し、ロボット支援下手術の位置付けを明確にするための議論を深めたい。 |
シンポジウム |
進行胃癌に対するminimally invasive conversion surgeryの現状セッション趣旨はこちら Conversion surgeryは、化学療法により切除可能となった進行胃癌に対する戦略として注目されているが、適応や術式の選択には統一されたコンセンサスがなく、施設ごとに方針が異なる。近年、免疫チェックポイント阻害剤を含む術前化学療法の有効性が示唆され、成績向上への期待が高まっている。本シンポジウムでは、適応、手術技術、術後成績、長期予後に関する最新エビデンスを共有し、今後の課題と展望について議論を深める。 |
シンポジウム |
食道癌に対するロボット手術の新展開セッション趣旨はこちら 食道癌に対する外科手術では、胸腔という環境での視野の制約や危険性の高い縦隔臓器や血管、神経があり、 |
シンポジウム |
ロボットで見えてきた局所微細解剖と新しいアプローチセッション趣旨はこちら 光学機器の発達とロボット支援手術の普及により、手ぶれのない精緻な操作が可能となり、微細な解剖学的構造の認識が飛躍的に向上してきている。これにより、より正確で再現性の高い手術手技が実現できるようになってきた。上部消化管領域における詳細な外科解剖に基づいたロボット手術の新たなアプローチや手技について供覧いただきたい。 |
シンポジウム |
低侵襲手術における噴門側胃切除術の再建法セッション趣旨はこちら 噴門側胃切除術(PG)は、早期胃癌や一部の進行胃癌に対する有効な治療選択肢として確立されつつあるが、再建法には依然として議論の余地がある。食道残胃吻合、間置空腸再建、ダブルトラクト再建など、各術式には利点と課題が存在し、術後の逆流防止や栄養状態の維持が重要な検討事項となる。本パネルディスカッションでは、各施設での再建法の選択基準、術後成績、合併症対策について議論を深め、最適な再建法の確立に向けた知見を共有する。 |
パネルディスカッション |
低侵襲手術における食道胃接合部癌に対する至適アプローチと再建セッション趣旨はこちら 食道胃接合部癌において、切除範囲や再建方法は治療成績に大きな影響を与える。手術技術の進歩により、最適なアプローチと再建方法を選択することが重要であり、患者の予後改善に繋がる可能性がある。本パネルディスカッションでは、食道胃接合部癌に対する最適な切除アプローチ、再建方法、およびそれらの治療成績を比較し、最新のエビデンスを元に議論を深めたい。 |
パネルディスカッション |
ロボット支援下食道切除術における上縦隔郭清のコツセッション趣旨はこちら 食道癌手術における上縦隔リンパ節郭清は、治療効果が高い一方で、反回神経麻痺による術後肺炎が予後に影響を及ぼす可能性があり、郭清精度と機能温存のバランスが重要である。胸腔鏡手術の普及により解剖の共通理解が進み、ロボット支援手術の導入で手ぶれのない精緻な操作が可能となってきた。再現性と精度の高い上縦隔郭清のコンセプトや手技の工夫について供覧いただきたい。 |
パネルディスカッション |
T4食道癌に対する内視鏡下手術セッション趣旨はこちら 2020年のNCDデータでは、食道切除術における低侵襲手術の割合は70%を超え、切除可能な食道癌に対する低侵襲手術は広く普及してきている。しかし、高度進行食道癌(T4)に対する内視鏡下手術の適応やアプローチは依然としてcontroversialである。根治性と安全性を両立させたT4食道癌に対する内視鏡下手術の実際と成績について供覧いただきたい。 |
パネルディスカッション |
残胃癌に対する低侵襲手術 至適郭清範囲と手技の工夫セッション趣旨はこちら 残胃癌に対する外科治療は、癒着の影響や解剖学的変化により技術的難易度が高く、低侵襲手術の適応や安全性について議論が続いている。ロボット支援手術や腹腔鏡手術を用いたアプローチでは、術野の展開や血管処理、リンパ節郭清における工夫が求められる。本ワークショップでは、残胃癌に対する低侵襲手術の適応、手術手技の工夫、合併症対策について、各施設の経験を基に議論を深める。発表者には、自施設での手術戦略や工夫、治療成績について報告いただきたい。 |
ワークショップ |
胃癌に対するロボット手術の長期成績セッション趣旨はこちら ロボット支援手術は胃癌手術において低侵襲性と精密な操作性を提供し、短期成績の向上が報告されている。一方で、長期成績に関するエビデンスはまだ限られており、生存率や再発率、機能的予後などの検討が求められる。本ワークショップでは、胃癌に対するロボット手術の長期成績に関する最新データを共有し、適応や課題、今後の展望について議論する。発表者には、それぞれの施設における治療成績や工夫、課題について報告いただきたい。 |
ワークショップ |
上部消化管外科領域のロボット支援下手術におけるトラブルシューティングセッション趣旨はこちら ロボット支援手術は上部消化管外科領域において精度の高い手術操作を可能にするが、術中・術後の予期せぬトラブルへの対応が重要となる。機器トラブル、術野の展開不良、吻合部関連合併症など、ロボット手術特有の問題が報告されている。本ワークショップでは、実際に遭遇したトラブルとその解決策、工夫について共有し、より安全なロボット手術の実施に向けた対策を議論する。発表者には、各施設の経験をもとに具体的な事例を紹介いただきたい。 |
ワークショップ |
食道癌に対するロボット手術の長期成績セッション趣旨はこちら ロボット支援下食道切除術は2018年4月に保険収載され、若手術者がロボット手術から食道手術を学ぶ機会が増えてきている。しかし、現在のロボット術者の多くは、開胸や胸腔鏡・縦隔鏡手術の経験を経たものがほとんどである。経験が積み重なった今、ロボット手術の長期成績を分析し、開胸および胸腔鏡手術/縦隔鏡手術と比較したロボット手術の有用性について供覧いただきたい。 |
ワークショップ |
縦隔鏡下食道切除術における工夫セッション趣旨はこちら 縦隔鏡下手術は、経胸的手術が困難な症例に対する有力な選択肢であり、一部の施設では切除可能食道癌に対する標準術式としても実施されている。しかし、狭い術野での操作や接線方向の視野確保、臓器の圧排など、技術的な習熟が必要である。安全かつ確実な縦隔鏡手術の普及を目指し、各施設における適応、アプローチ(左頸部/両側頸部)や手技の工夫について発表いただきたい。 |
ワークショップ |
| 下部消化管領域 | セッション形式 |
|---|---|
結腸癌に対する体腔内吻合の成績と今後の展望セッション趣旨はこちら 近年、結腸癌の手術において体腔内吻合で再建する症例が増加している。その方法や適応に一定の見解はなくいまだ標準治療には至っていない。ここではロボット、腹腔鏡での各施設の適応、方法のもとでの長期成績を示していただき、特に腫瘍学的安全性に注目して発表していただきたい。また再発症例に関しても検討いただき、今後の展望について述べていただきたい。 |
シンポジウム |
精密性とコストの両立を目指したロボット支援下大腸癌手術セッション趣旨はこちら ロボット支援大腸癌手術は、高精度な操作性と優れた視認性により、近年ではその短期成績/長期成績に関する良好な報告が散見されている。一方で、高額な医療費や手術時間の延長といった課題も抱えている。本セッションでは、ロボット支援下大腸癌手術における精密性とコストのバランスに焦点を当て、臨床的・経済的な観点から議論して頂きたい。 |
シンポジウム |
ロボット支援直腸癌手術の短期および長期成績セッション趣旨はこちら 直腸癌手術においてはロボット支援手術の割合が大きく増加し、第一選択とする施設も増加した。各施設において症例集積が進んできた現在における、短期および長期成績について現状を提示していただきたい。また手術時間の延長やコストの増加などの問題点も指摘されており、これらについても多角的な点から検討して発表していただきたい。 |
シンポジウム |
TNT後の直腸癌手術の現状と治療成績セッション趣旨はこちら Total Neoadjuvant Therapy(TNT)は、局所進行直腸癌に対する集学的治療として注目されており、長期成績の向上や局所 |
パネルディスカッション |
大腸癌に対するロボット手術の教育を考えるセッション趣旨はこちら ロボット支援下手術は、精度の高い操作を可能にし、低侵襲な手術の実現に寄与している。しかし、ロボットの保有の有無による |
パネルディスカッション |
他臓器合併切除を伴う直腸癌手術の適切なアプローチセッション趣旨はこちら 他臓器浸潤を伴う直腸癌手術は、高難度の手技として適切なアプローチによる安全な手術が求められる。近年はこの分野にも腹腔鏡手術、ロボット支援手術、そして経肛門・経会陰アプローチが取り入れられるようになってきた。それぞれの方法の詳細とともに利点やピットフォールを提示していただき、適切なアプローチについて議論していただきたい。 |
パネルディスカッション |
直腸癌局所再発に対する腹腔鏡下手術セッション趣旨はこちら 直腸癌術後の局所再発においては、放射線療法、化学療法、化学放射線療法、切除などの組み合わせが考慮される。また手術においては、鏡視下手術の利点が報告されるが、その適応および腹腔鏡手術、ロボット支援手術のいずれかの選択も議論がある。鏡視下手術の有用性や限界、手術手技、合併症、腫瘍学的成績・予後について検討を頂き、直腸癌局所再発に対する鏡視下手術の適応について議論をいただきたい。 |
パネルディスカッション |
腹腔鏡下大腸癌手術におけるベストプラクティスセッション趣旨はこちら 腹腔鏡下大腸癌手術は低侵襲でありながら根治性を確保することが求められる。本セッションでは、安全かつ効率的な手術のためのベストプラクティスを検討し、術後合併症の低減と短期・長期成績の向上を目指し、より良い治療成績に貢献することを目的とする。最適なポート配置、視野の展開、適切な剥離層の選択、神経温存の工夫、吻合方法など、各施設の取り組みに関して発表いただきたい。 |
パネルディスカッション |
経肛門アプローチのコツとピットフォールセッション趣旨はこちら 早期直腸癌に対しては、ESDの進歩により大腸内視鏡治療が多く行われるようになった。一方、経肛門アプローチは粘膜下腫瘍の切除や全層切除などさらに広い適応があり進行癌の根治切除にも利用されるものの、狭い管腔内での手術操作の難易度は高い。各施設における手術手技の工夫を提示していただきコツとピットフォールについて発表していただきたい。 |
ワークショップ |
IBDに対する低侵襲手術とその工夫セッション趣旨はこちら 炎症性腸疾患(IBD)に対する外科治療では、低侵襲手術の導入により患者の負担軽減が期待される。本セッションでは、IBDにおける腹腔鏡手術の利点と課題を踏まえ、術式選択、最適なポート配置、吻合方法、適切なエネルギーデバイスの使用、術後管理の標準化などについて考察する。術後合併症の低減と機能温存を目指し、IBD患者にとって最適な低侵襲手術戦略を探る。 |
ワークショップ |
新規ロボットによる大腸切除術の新展開セッション趣旨はこちら 近年、ロボット支援下手術は大腸切除術において急速に普及しており、新たな手術支援ロボットの登場により、さらなる低侵襲化、 |
ワークショップ |
大腸癌に対するロボット支援手術のプロクター制度の現状と課題セッション趣旨はこちら ロボット支援下大腸癌手術は、精度の高い手術操作を可能にし、低侵襲性や安全性の向上が期待されている。その普及と技術の |
ワークショップ |
| 肝胆膵領域 | セッション形式 |
|---|---|
ロボット肝切除の最前線セッション趣旨はこちら ロボット支援下肝切除が保険適応となってから約3年が経過し、多くの施設でロボット肝切除が導入されている。ロボット特有の三次元視野や精密な操作性を活かした手術手技の進化、安全性向上、合併症の低減などが期待されている。そこで、本セッションでは、各施設での導入状況や手術成績に関する最新データをご提示いただき、腹腔鏡手術との比較を含めた今後のロボット技術を活用した肝切除の展望について議論していただきたい。 |
シンポジウム |
手術支援テクノロジーがもたらす低侵襲肝胆膵手術の現状と展望セッション趣旨はこちら 低侵襲肝胆膵手術領域において多彩なテクノロジーが開発され、すでに実臨床において応用、定着してきている。本セッションでは、AR/VR/MR、遠隔手術、シミュレーション、ナビゲーション、蛍光ガイドナビゲーションに至るまで、現在までに開発されてきたこれらの手術支援テクノロジーがもたらした低侵襲肝胆膵手術の進歩について提示いただき、今後の方向性についても議論していただきたい。 |
シンポジウム |
膵癌に対するロボット支援膵切除術の適応と郭清方法の工夫セッション趣旨はこちら 近年、膵癌に対するロボット支援膵頭十二指腸切除術(RPD)が一部の施設で行われるようになっているがその適応は各施設で異なり、SMAや門脈周囲への進展例をどのように扱うか検討が必要である。一方、SMA周囲の郭清では、根治性だけでなく安全性や手術時間短縮も課題であり効率的なアプローチが求められる。本セッションでは、各施設の適応基準、郭清方法について報告いただき、RPDの位置づけを議論していただきたい。 |
シンポジウム |
急性胆嚢炎に対する低侵襲手術の現状と課題セッション趣旨はこちら 急性胆嚢炎に対する手術は重症度によりその手術難度が非常に異なる。炎症や線維化の強い症例は亜全摘などの手術が行われ、手術時期の選択、手術方法の選択に難渋することがある。本シンポジウムでは急性胆嚢炎に対する低侵襲手術における各施設の現状をご提示いただき、重症胆嚢炎に対する手術手技と短期長期成績についてエビデンスを含めた発表をいただきたい。 |
シンポジウム |
S7,S8領域の低侵襲肝切除を安全に施行するための工夫セッション趣旨はこちら S7およびS8領域における肝切除は様々な理由で難易度が高いとされている。本セッションでは、本術式を安全かつ効果的に行うための具体的な術式や技術的工夫を提示していただき、特に、術中の視野確保、グリソン処理、止血方法における最新の工夫や技術を議論していただきたい。さらに、各施設の具体的なアプローチを通じて、安全性と手術成績を向上させるための工夫についてもご提案いただきたい。 |
パネルディスカッション |
胆道癌における低侵襲手術の現状と課題セッション趣旨はこちら 胆嚢癌において胆嚢床切除による腹腔鏡下手術や胆管癌に対する腹腔鏡下、ロボット支援下手術が保険収載され、胆道癌における低侵襲手術が注目されている。しかし、未だ症例集積は少なく、各施設の課題もある。本ワークッショプでは胆道癌における低侵襲手術の各施設の現状とその問題点につき議論していただきたい。 |
パネルディスカッション |
低侵襲尾側膵切除術:腹腔鏡下手術 vs ロボット支援手術セッション趣旨はこちら 尾側膵切除術では腹腔鏡下手術が広く行われ、近年はロボット支援手術の導入も増えている。ロボット支援手術は精緻な操作性や視認性が利点である一方、腹腔鏡下手術はエネルギーデバイスの性能が優れ、術野展開のしやすさが特徴である。また膵癌や脾動静脈温存手術では、それぞれのアプローチにおける利点・欠点が異なる可能性がある。本セッションでは、両者の特性を比較し、各疾患においてどちらが有用かを議論していただきたい。 |
パネルディスカッション |
ロボット支援肝切除における肝実質切離の方法セッション趣旨はこちら ロボット支援下肝切除における肝実質切離方法はCrush-Clamp法が主であるが、施設によっては助手によるCUSAを使用したTwo Surgeon Techniqueも行われている。本セッションでは、ロボット肝切除における肝実質切離について各施設の方法をご提示いただき、その利点・欠点を議論していただきたい。さらには今後の展望にも触れていただきたい。 |
パネルディスカッション |
ロボット支援手術におけるFusion Surgery -肝胆膵外科領域での有用性を探る-セッション趣旨はこちら 肝胆膵外科におけるロボット支援手術は増加しているが、手術時間の延長が課題であり、導入時や若手指導に伴う時間延長は人件費増大の要因となる。また、ロボット支援手術のエネルギーデバイスは腹腔鏡下手術より精度が低く時間延長を招く。一方、胃外科では腹腔鏡下手術のデバイス活用が進み、肝胆膵外科でもその技術の応用が期待される。本セッションでは、Fusion Surgeryの有用性について議論していただきたい。 |
パネルディスカッション |
低侵襲肝胆膵手術におけるトラブルシューティングセッション趣旨はこちら 肝胆膵低侵襲手術の普及に伴い、出血や臓器損傷などのトラブルに対する内視鏡的な新たな解決策や、従来の開腹手術とは異なるアプローチが求められています。またロボット支援下手術が普及してきた昨今では、ロボット特有のトラブルも散見されている。本セッションでは、腹腔鏡またはロボット支援下における肝胆膵手術でのトラブルの際の具体的な事例や技術的工夫をご提示ただき、その対処方法について議論していただきたい。 |
ワークショップ |
ロボット支援膵頭十二指腸切除における再建の工夫セッション趣旨はこちら 膵頭十二指腸切除術において、術後合併症の低減は重要な課題である。ロボット支援手術は膵再建や胆道再建が行いやすいとされているが、その具体的な手技や再建方法は施設ごとに異なり、最適なアプローチについて統一された見解は得られていない。本セッションでは、各施設におけるロボット支援膵頭十二指腸切除術の膵再建および胆道再建の手術手技に焦点を当て、技術的工夫や手術成績について報告していただきたい。 |
ワークショップ |
低侵襲再肝切除術の適応と限界セッション趣旨はこちら 低侵襲肝切除が普及してきた現在では、再肝切除の症例も腹腔鏡下またはロボット支援下に行われるようになってきている。本セッションでは再肝切除における低侵襲手術の適応基準とその限界について言及していただきたい。初回手術後の癒着やPringle法困難な症例に対する手技や初回手術時の対策も含めて各施設の工夫を含めて発表していただきたい。 |
ワークショップ |
低侵襲尾側膵切除術における膵切離法の工夫セッション趣旨はこちら 低侵襲尾側膵切除術において、膵液瘻の発生率を低下させるには適切な膵切離が重要である。一般的に自動縫合器が使用されるが膵が厚い症例では膵液瘻のリスクが高まり工夫が求められる。膵の圧縮は有用とされるが、その方法や圧縮時間は施設ごとに異なり膵裂傷時の対応も課題である。ロボット支援手術では腹腔鏡用ステープラー使用時に工夫が必要となる。本セッションでは、膵切離の工夫やその成績について報告していただきたい。 |
ワークショップ |
良性胆道疾患に対する低侵襲手術の現状と課題セッション趣旨はこちら ロボット支援総胆管拡張症手術があらたに保険収載され、総胆管拡張症や総胆管結石症といった良性胆道疾患に対する低侵襲手術が注目されている。本セッションでは良性胆道疾患に対する開腹、腹腔鏡下、ロボット支援下それぞれの現時点での適応、短期・長期成績および低侵襲手術の技術的なピットホールについても議論していただきたい。 |
ワークショップ |
| ヘルニア領域 | セッション形式 |
|---|---|
成人鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡手術の現状と課題セッション趣旨はこちら 腹腔鏡下鼠径部ヘルニア手術は国内において成人鼠径部ヘルニア手術全体の50%を超え、主要な術式となっている。しかし、腹腔鏡手術は未熟な術者が行うと合併症や再発のリスクを伴い、ヘルニアの状態によっては第一選択の手術ではないという考え方もある。それぞれの施設の成人鼠径部ヘルニア手術の現状と課題を報告し、腹腔鏡下鼠径部ヘルニア手術の将来を展望していただきたい。 |
シンポジウム |
リスクのある腹壁ヘルニアの治療方針セッション趣旨はこちら リスクのある腹壁ヘルニアでは、感染、再発、疼痛などの合併症を防ぎつつ、確実な修復を目指す必要がある。 |
パネルディスカッション |
LPEC法 成人への適応セッション趣旨はこちら LPEC法は2000年以降小児ヘルニア手術において普及し、現在ではほぼ半数の小児症例に対して行われている。さらに、最近では成人症例への適応の可能性も模索され、人工物を使用しない腹腔鏡手術として関心が高まってきている。 |
ワークショップ |
ロボット支援鼠径部ヘルニア手術の現状と将来セッション趣旨はこちら ロボット支援手術は悪性腫瘍を主体に、国内では手術件数が急速に増加している。しかし、鼠径部ヘルニアに対しては保険診療が認められていないため、特定の施設において自費診療で行われているのが現状である。成人鼠径部ヘルニアに対するロボット手術のメリットとデメリット、費用対効果などを報告していただき、ロボット手術の現状と将来を語っていただきたい。 |
ワークショップ |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術を前提とした前立腺がん手術の可能性セッション趣旨はこちら 本学会でも何度も議論されてきているが、前立腺全摘除術後の鼠径部ヘルニア手術、鼠径部ヘルニア術後の前立腺全摘除術はどちらも難易度が高く定型化が難しい。今回は、相互の手術を意識したお互いのプライマリー手術をどのようにしたらよいかについて、泌尿器科・外科のそれぞれ立場から議論をしていただきたい。 |
パネルディスカッション |
脱出部位が複雑な腹壁ヘルニア(腰ヘルニア、心窩部ヘルニア、恥骨上ヘルニアなど)の最適な治療セッション趣旨はこちら 腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡手術は、IPOMやIPOM-plus、eTEP、eTEP-TAR、eMILOS、SCOLAなどが行われているが、それぞれの手術には利点と欠点がある。絶対的な手術術式がない中で、手術方法の選択は各施設に任せられており、ヘルニアの部位や状態が複雑な場合は治療法の選択はさらに困難となる。それぞれの複雑な腹壁ヘルニアに対して最適な手術方法について討論していただきたい。 |
パネルディスカッション |
| 呼吸器外科領域 | セッション形式 |
|---|---|
精緻な胸腔鏡下肺区域切除術(ロボット含む)セッション趣旨はこちら JCOG0802試験で区域切除が2cm以下の早期肺がんに対して有用性が示されて、標準治療の選択肢となっている。その後、区域切除が増加している。区域切除では、解剖学的区域に基づいた精密な切除が求められる。本シンポジウムでは、様々な工夫により精緻な区域切除を行う方法について発表していただきたい。 |
シンポジウム |
若手呼吸器外科医に対する胸腔鏡下手術(ロボットを含む)の教育セッション趣旨はこちら 胸腔鏡下手術に加え、ロボット手術も急速に普及し始めている。それに伴い、開胸手術の実施方法や外科教育のあり方も変化しており、研修医や若手外科医に対して、個々の技量に応じた質の高い教育が求められている。胸腔鏡手術と比較すると、開胸手術は胸腔内での出血時の対応が容易である。一方、胸腔鏡下手術やロボット手術では、経験の浅い外科医の修練を安全に行うための教育体制が重要となる。また、胸腔鏡安全技術認定制度は、医療安全の観点から、胸腔鏡手術の安全な実施を目的とした制度である。この制度により、胸腔鏡手術を行う医師の技術が客観的に評価・認定される。本制度を踏まえ、今後の外科教育について議論したい。 |
シンポジウム |
呼吸器外科ロボット手術とコスト対策セッション趣旨はこちら 呼吸器外科領域でも肺がんに対するロボット支援手術の保険収載は、2018年4月から開始された。 |
シンポジウム |
胸部悪性腫瘍の拡大手術における低侵襲アプローチの応用: 胸腔鏡下手術(ロボットを含む)vs 開胸セッション趣旨はこちら 早期の悪性腫瘍に対して、低侵襲手術として胸腔鏡下手術や単項式手術が行われるようになった。近年では、進行した悪性腫瘍に対してもロボット手術や胸腔鏡下手術が導入されてきている。拡大手術では、開胸手術を行っている施設も多い。それぞれの手術の長所、短所をふまえて議論したい。 |
パネルディスカッション |
原発性肺癌におけるロボット支援下肺区域切除術の手術成績セッション趣旨はこちら 2018年4月から肺がんに対するロボット支援下肺葉切除術が保険適用となった。その後、2022年4月には肺区域切除にも適応拡大された。一方でJCOG0802で区域切除の有効性が示されて以来、区域切除は増加している。ロボット支援下肺区域切除は各施設で行われており、本ワークショップでは、手術成績について議論したい。 |
ワークショップ |
呼吸器外科領域のおけるロボット支援下手術の術中術後合併症の原因とその対策セッション趣旨はこちら ロボット支援下手術では、精密な手術が可能とされる。しかし、ロボット支援下手術では、開胸手術や胸腔鏡下手術と比べて、利点のみでなく欠点もある。一般的に触覚がないことが短所として挙げられている。そのため、ロボット支援下手術に特有な、術中術後合併症もある。その原因と対策について発表していただきたい。 |
ワークショップ |
肺癌に対するReduced port VATSおよびRATSのKnack&Pitfallsセッション趣旨はこちら 低侵襲手術をめざして、呼吸器外科領域に胸腔鏡下手術(VATS)や最近ではロボット支援下手術(RATS)が導入されている。一方で、特にRATSでは、米国で確立された5ポートが主流であった。低侵襲を目指した手術である一方で、RATSで5ポートの穴を開けることに疑問がある。VATSではユニポートで行われることも多くなってきている.ポートの数を減少する要点とピットフォールについて議論したい。 |
ワークショップ |
縦隔腫瘍に対する低侵襲手術セッション趣旨はこちら 縦隔は左右の肺、胸骨、大血管、心臓などの重要臓器に接しているため、これまで安全なアプローチとして、胸骨正中切開による侵襲の高い手術が行われてきた。しかし近年では、医療機器の進歩により、周囲臓器の合併切除を要するような症例においても、胸腔鏡を用いた低侵襲な手術が行われることが増えている。さらに、縦隔腫瘍に対するロボット支援手術が保険適用となり、多くの医療機関で導入が進んでいる。本セッションでは、こうした種々の低侵襲な手術法による縦隔腫瘍治療について議論したい。 |
パネルディスカッション |
| 小児外科領域 | セッション形式 |
|---|---|
小児外科疾患に対する内視鏡外科手術導入による長期予後の変化セッション趣旨はこちら 小児外科領域においても様々な内視鏡手術が提案されてはいるが、その有効性には議論の余地がある。本シンポジウムではその手術手技と長期の治療成績およびそのエビデンスに関して発表していただきたい。 |
シンポジウム |
どうやって内視鏡手術の技術を高めますか?(世代別)セッション趣旨はこちら 小児外科領域において内視鏡手術が導入され、確立された治療の一つではあるが、内視鏡手術のトレーニングは重要課題である。若手からベテランまでがどのようにして内視鏡手術の技術向上を図っているか現状を議論することで本邦の内視鏡手術が進むべき道を明らかにする。 |
パネルディスカッション |
技術認定制度の意義:小児に対する内視鏡外科手術の成績と安全性は向上しているのか?セッション趣旨はこちら 小児外科領域における技術認定医制度意義を踏まえて技術認定取得者のかかわりの有無と手術成績および安全について、各施設の現状を発表いただきたい。 |
パネルディスカッション |
小児縦隔腫瘍に対するアプローチ(胸腔鏡 vs 縦隔鏡 vs ロボット)セッション趣旨はこちら 小児縦隔腫瘍に対しては根治性観点から、開胸手術が一般的であったが、術後の整容性や胸郭変形などから、、近年では安全性と根治性を担保にし術後QOLに配慮して内視鏡手術も導入する施設も増えててきている。各施設による術式選択や経験について発表していただき、その課題を明らかにする。 |
パネルディスカッション |
小児外科領域でどのようにロボット支援手術を普及させていくのかセッション趣旨はこちら 成人領域ではロボット支援手術が急速に広まっており、小児外科領域でも2018年に縦隔良性悪性腫瘍手術・2020年に腎盂形成手術・2022年に総胆管拡張症手術が保険収載され、適応拡大がされつつあるが、未だに十分とは言い難い。今後、安全なロボット支援導入および普及に向けた課題などを議論したい。 |
ワークショップ |
小児内視鏡外科手術における最新技術の活用セッション趣旨はこちら 内視鏡外科領域において多彩なテクノロジーが開発され、すでに実臨床において応用してきているものもある。本セッションではエネルギーデバイスから、蛍光ガイドナビゲーション、AR, VR, MR、ナビゲーション、シミュレーション、遠隔手術に至るまで、現在までに開発されてきたテクノロジーのこれまでと今後の展開についてご発表いただく。 |
ワークショップ |
| 産科婦人科領域 | セッション形式 |
|---|---|
技術認定の自動化に挑むセッション趣旨はこちら 内視鏡手術の技術認定においては、審査員により手術動画が審査される。各審査員の評価にはバラツキがあり複数人による審査が望ましいが、1件の審査に多くの人員を割くことはできない。AIなどによる動画審査の自動化がなされれば、公正な審査が可能となる。本ワークショップでは、動画審査の自動化についての最新の取り組みについて発表してもらいたい。 |
ワークショップ |
子宮体癌の内視鏡手術セッション趣旨はこちら 平成26年に腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体癌に限る)が、平成30年には腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体癌に対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)が保険収載され、多くの低侵襲子宮体癌手術が行われるようになった。しかし、これらは対象が早期子宮体癌に限られ、進行子宮体癌に対する内視鏡手術は未だ保険適用にない。本シンポジウムでは、子宮体癌に対する低侵襲術の最新の取り組みについて発表してもらいたい。 |
シンポジウム |
腹腔鏡下骨盤内臓全摘術セッション趣旨はこちら 令和6年に腹腔鏡下骨盤内臓全摘術が保険収載されたが、高難度術式のため全国的に普及しているとは言い難い。骨盤内臓全摘術が低侵襲になされれば患者にとっての福音である。同手術の具体的な手技と長期の治療成績およびその有効性に関して発表してもらいたい。 |
ワークショップ |
妊孕性向上のための子宮筋腫の最新手術セッション趣旨はこちら 晩産化により、不妊の原因としての子宮筋腫がクローズアップされるようになってきた。妊孕性温存のために腹腔鏡下筋腫摘出術や子宮鏡下筋腫切除術が行われるが、子宮に愛護的な操作が求められる。本シンポジウムでは妊孕性向上のための手術手技と治療成績およびその有効性に関して発表してもらいたい。 |
シンポジウム |
| 泌尿器科領域 | セッション形式 |
|---|---|
安全なロボット支援腎尿管全摘術セッション趣旨はこちら 腹腔鏡手術からロボット支援手術に移行しつつあるが、前立腺や膀胱の手術とは異なり術野が上腹部から下腹部にわたるためカメラポートの変更やポート位置の工夫などが必要となる。経験豊富な施設における術式の工夫、治療成績などについて発表してもらいたい。 |
ワークショップ |
ロボット支援・AI技術を用いた前立腺肥大症に対する手術療法セッション趣旨はこちら 従来の内視鏡的切除術、前立腺核出術に加えて近年前立腺肥大症に対する新規医療機器が次々と開発されている。最新の治療法を紹介するとともにその経験、手術成績について発表していただきたい。 |
ワークショップ |
高度進行腎癌に対する手術セッション趣旨はこちら 従来行われていた高度進行腎癌も開腹手術とともにロボット支援手術が適応されるようになってきている。安全性の確保が最も重要な課題であり、ハイボリュームセンターの治療成績を報告するとともに導入に関する注意点などを概説していただきたい。 |
シンポジウム |
ロボット支援膀胱全摘除術の合併症の予防と対策セッション趣旨はこちら 膀胱全摘術もロボット支援手術が標準となってきているが、合併症の報告も少なくない。本シンポジウムではロボット支援膀胱全摘術の合併症の予防や対策について発表していただく。 |
シンポジウム |
ウロギネコロジーセッション趣旨はこちら 泌尿器科と産婦人科の境界領域にある疾患を取り扱うウロギネコロジーですが、子宮脱・膀胱脱・直腸瘤などの骨盤臓器脱や尿失禁、頻尿、夜間頻尿などの排尿のトラブル、便失禁や直腸脱などの排便のトラブルなど多岐にわたります。近年は腹腔鏡やロボット支援手術も広く行われています。手術適応や成績について専門施設の成績を報告していただくとともに、注意点等について概説していただきたい。 |
シンポジウム |
| 肥満外科・形成外科領域 | セッション形式 |
|---|---|
減量・代謝改善手術の今後の展望セッション趣旨はこちら 減量・代謝改善手術が日本で行われるようになって20年以上が経った。腹腔鏡下スリーブ状胃切除術が保険適応となって10年、スリーブバイパス術は昨年保険適応となったが、未だ他のアジア諸国と比較すると、施行件数は少ない。日本で適正に行われるために、何が必要で今後どのような発展を遂げるべきなのかを、世界の中の日本というポジションから検討していただきたい。 |
シンポジウム |
スリーブplusをどう選ぶ?それぞれの特徴と選択のポイントセッション趣旨はこちら 2024年から腹腔鏡下胃縮小術(バイパスを伴うもの)が保険適応となり、日本でも術式の選択がひろがった。しかし、保険術式の文言の解釈により、先進医療であった従来の腹腔鏡下スリーブ状胃切除+十二指腸空腸バイパス術のみでなく、すべてのスリーブplusバイパス術が行えるようになった。新たな広がりをみせるスリーブplusの特徴と選択、その可能性を検討していただきたい。 |
パネルディスカッション |
合併症軽減を見据えたこだわりのスリーブ状胃切除術セッション趣旨はこちら スリーブ状胃切除術の合併症には出血、縫合不全、GERD、通過障害、体重減少不良、体重リゲインなどがあり、一度生じると難治性であることがおおい。スリーブ状胃切除術自体はシンプルな術式であるが、シンプルであるからこそこだわるべきポイントも多い。このセッションではエキスパートのこだわるポイントに関して討議していただきたい。 |
ワークショップ |
| 乳腺外科領域 | セッション形式 |
|---|---|
乳癌に対する内視鏡およびロボット支援下手術の未来セッション趣旨はこちら ロボット支援下手術の適正使用指針の発表や薬事承認を契機に、近年、乳腺領域においても内視鏡およびロボット支援下手術が注目されている。一方で、術式の普及には、エビデンスの確立や手術手技の標準化など、さまざまな要素が不可欠である。本パネルディスカッションでは、現状における内視鏡下およびロボット支援下乳輪温存乳房切除術の利点や課題を明らかにし、今後の展開について議論を深めていただきたい。 |
パネルディスカッション |
| 移植領域 | セッション形式 |
|---|---|
生体ドナー手術に対する低侵襲手術の現状と課題セッション趣旨はこちら 生体ドナー手術は安全性を担保しつつ低侵襲化が望まれる。生体腎移植ドナー手術は多くの症例が鏡視下で施行されているが、アプローチ法や整容性等様々な工夫がある。生体肝移植ドナー手術は外側区域グラフト採取のみが鏡視下の保険適応で、実施施設はまだ限定的だが、保険適応拡大も含めてさらなる普及が望まれている。本セッションでは生体ドナーに対する低侵襲手術の現状と、今後の展開・課題について議論していただきたい。 |
パネルディスカッション |
| 心臓血管外科領域 | セッション形式 |
|---|---|
内視鏡下心臓手術はロボットが主流となっていくのかセッション趣旨はこちら 内視鏡下心臓手術において、ロボットによる手技が主流となるのかについて議論する。ロボットの優位性とともにロボットを用いない内視鏡下手術の優位性をエキスパートに論じていただきたい。今後、ロボットが主流となるための課題 (専門制度、チーム、技術、ロボット自体の進化)について議論を深めていただきたい。 |
パネルディスカッション |
| 領域横断領域 | セッション形式 |
|---|---|
ロボット支援手術:ロボット手術の新たな展開セッション趣旨はこちら 各外科領域でロボット手術の割合が急速に増加しており、集約化から均てん化の段階に突入し日常臨床化している。今後は適応の拡大、遠隔手術への利用や新たな機能の開発、付加、デジタル機器を併用した手術支援など、様々な新展開が既に開始されている。ロボット手術の次の進化をそれぞれの観点から講演いただきたい。 |
シンポジウム |
ロボット支援手術:ロボット手術時代の手術室運営の課題セッション趣旨はこちら ロボット手術が急速に普及し、施設における増設や新機種の導入なども経験される。各領域での内視鏡手術とロボット手術の棲み分けも工夫が必要である。実務面でも共有における各領域の連携、トラブルシューティングを含む若手・多職種チーム教育など課題も増えている。また、ロボット手術の経済面も注視すべき事項である。ロボット手術時代の手術室運営を広い観点から考察いただきたい。 |
パネルディスカッション |
ロボット支援手術:地域医療施設におけるロボット手術セッション趣旨はこちら ハイボリューム施設ではロボット手術が定型手術の一つとして認識されるに至った。地域医療圏の中心的な施設にもロボット手術システムが導入され、ハイボリューム施設とは異なった独自の工夫や診療領域間での共有があるかと想像する。教育やトラブルシューティングなどそれぞれの特性を情報発信いただきたい。 |
ワークショップ |
ロボット支援手術:遠隔手術の実現に向けてセッション趣旨はこちら ロボットを用いた遠隔手術は地方施設におけるロボット手術の支援が可能となり、医療安全、患者移動の不要や医師の地域偏在の対策にもなり得る。現在、実証実験を行いつつ、デバイス開発、通信環境確認、トラブルシューティングに関する検討やコスト面での課題解決に努力している段階である。近い将来の実臨床に向けた現状の報告や考察をお願いしたい。 |
パネルディスカッション |
ロボット支援手術:トラブルシューティングセッション趣旨はこちら ロボット手術が各領域で急速に増加しており、適応術式の増加とともに施行施設もハイボリューム施設から地域医療の中心施設にも拡大している。術者も開腹・開胸手術、内視鏡手術の次にロボット手術を施行している年代から内視鏡手術とロボット手術を並行して検している若い年代までバックグラウンドはまちまちである。安全性の担保も重要であり、安全教育、事故予防やトラブルシューティングなどの工夫を共有いただきたい。 |
ワークショップ |
外科教育:低侵襲手術時代の手術教育セッション趣旨はこちら 現在は開腹・開胸手術、内視鏡手術、ロボット手術の手術がそれぞれの利点を有しながら存在している。すべてを修得するための手術教育を確立する必要がある。低侵襲手術が優勢なため、若い世代の開腹・開胸手術の経験不足も指摘されるが、逆にロボット手術の早期開始も叫ばれている。新規教育コンテンツや器具なども含め、教育法に関する意見交換をしたい。 |
シンポジウム |
外科教育:ロボット手術時代の技術認定制度のあり方セッション趣旨はこちら 各領域の専門医資格を取得した医師が次に目指す資格として技術認定がある。内視鏡手術とロボット手術が並走している状況において、技術認定医像も変っていく可能性もある。 |
ワークショップ |
すべての内視鏡外科医がいきいきと働ける環境整備のためにセッション趣旨はこちら 外科医の働き方が多様化し、ライフステージに応じたキャリア形成や多様な選択肢についての議論が重要となっている。本セッションでは、これまで検討されてきたジェンダーギャップにとどまらず、地域・診療領域における格差など、あらゆる場面で生じうるさまざまなギャップに着目する。外科医が不足する未来が予測される中、すべての内視鏡外科医が年代やキャリアステージに応じて力を発揮できる環境整備が不可欠である。個々が抱える問題を補い合い、支え合うための具体的な支援策を模索しながら、誰もが生き生きと働ける職場づくりに向けた多様な提言を共有する場としたい。 |
シンポジウム |
外科医師の未来を拓く:多様性を考慮した指導者育成とキャリアパスの構築セッション趣旨はこちら 外科医療の発展には、多様な背景を持つ医師が活躍できる環境づくりが不可欠です。 |
ワークショップ |
AI・新規医療:外科医療におけるAIの活用セッション趣旨はこちら AIの利用が医療にも定着しつつあり、その役割は年々拡大している。画像、内視鏡診断や病理診断から始まり、今後はRadiomicsへと発展しよう。外科領域では手術のナビゲーションや技術評価にも導入されている。今後も手術支援や教育にも拡大していく可能性が高いと考える。現在、開発中、試用しているAIの用途や特性に関する情報発信をお願いしたい。 |
シンポジウム |
AI・新規医療:ナビゲーション支援の現状と将来セッション趣旨はこちら 様々な手術にナビゲーションを用いて手術支援を行うことが一般的になってきた。ナビゲーション画像を患者に投影して、より実効的な手術支援を行ったり、3Dバーチャル画像を用いて術中の複雑な解剖を把握しやすくしたり、方法も多種存在する。教育の一部としても採用されており、さらに高次なナビゲーションも開発されている。この領域の現状と将来につき論じていただきたい。 |
ワークショップ |
AI・新規医療:新規医療技術セッション趣旨はこちら 新たな医療機器の開発品が高速で実臨床で使用されるようになってきた。ロボット手術やAIのほか、医療のDX化を構成する有用なシステムは多数存在する。医工連携の新しい成果であったり、スマートホスピタルの一部として、医師のタスクを軽減しながら医療の質を向上させる内容などの情報共有いただきたい。 |
パネルディスカッション |
その他:大規模データからみた低侵襲手術の現状セッション趣旨はこちら 我が国の内視鏡外科手術をはじめとする低侵襲手術の技術レベルは高く、術後の合併症も低率であると認識されている。ロボット手術に代表されるように、新たな外科医療も開始されている。各領域の外科医療の安全性、予後、適応の拡大などに関する多施設研究、大規模データの解析により、外科医療の現状を可視化できる発表を募集する。 |
シンポジウム |
その他:外科医を増やす新たな取り組みセッション趣旨はこちら 外科医数の減少が以前より指摘されている。同時に地域偏在や診療科偏在も我が国の課題であり、さまざまな原因の解析や就労環境の改善が目標とされる。ワークライフバランスへの配慮、研修プログラムの工夫、タスクシフト、インセンティブなど外科系の魅力を増すために努力が必要とされる。工夫されている取り組みを共有し意見交換するセッションとしたい。 |
ワークショップ |
内視鏡外科と環境問題 -Green Surgeryへの道ーセッション趣旨はこちら 地球温暖化・環境問題の重大性が増す中、医療分野においてもCO2削減等の諸対応が求められている。内視鏡外科手術やロボット支援手術は環境面で多くの問題や課題を抱えている。欧米の外科系学会では数年前から環境問題への取り組みを始めているが、JSESでも将来構想委員会での検討を経て2024年に『環境問題に関するワーキンググループ』を立ち上げ、活動を開始した。本セッションでは環境問題への理解を深めることと共に、内視鏡外科医が取り組める内容を議論する。 |
シンポジウム |
その他:これからの医工連携、事業化セッション趣旨はこちら 内視鏡外科は医工連携の成果に恵まれた領域である。しかし、従来の企業が開発した器具や製品を臨床で試用し評価するスタイルから、今後は外科医がはじめから企業との開発に参画したり、あるいは特許を取得し主体的に起業する場合もあり得ると思われる。これからの医工連携や事業化に関する新たな可能性を討議したい。 |
パネルディスカッション |
外科医減少の中での手術の工夫セッション趣旨はこちら 外科医の減少が進む中、限られた人的資源で安全かつ高品質な手術を提供する工夫が求められている。本セッションでは、手術支援ロボットやナビゲーション技術の活用、標準化された手術手技の確立、タスクシフトによるチーム医療の推進、若手外科医の教育・トレーニングの工夫について検討する。これらの取り組みにより、外科医不足の状況下でも安定した手術成績を維持し、持続可能な外科医療の実現を目指す。 |
ワークショップ |
| 医工連携領域 | セッション形式 |
|---|---|
医工連携研究を始める方法セッション趣旨はこちら 近年、医工連携研究が注目され、医師による研究として広く受け入れられるようになりました。本セッションでは、実際に医工連携研究を通じて新規医療機器を開発・上市した経験者が、手続きの流れ、チームの組成、資金調達、企業との連携方法などを具体的に解説します。聴講者が医工連携研究を始めるきっかけとなるようなセッションを共に創る先生方の参加を募集します。 In recent years, medical-engineering collaboration research has been attracting attention and has become widely accepted as a form of physician-led research. In this session, a person who has developed and launched a new medical device through medical-engineering collaboration research will give a concrete explanation of the procedures, team formation, fund procurement, and collaboration with companies. We are looking forward to the participation of doctors who will create a session that will provide an opportunity for the audience to start research on medical-engineering collaboration. |
シンポジウム |
外科医による医療機器開発 〜其の伍〜 開発後のリアルセッション趣旨はこちら 2021年より本シリーズ企画を重ねて参りしたが、近年、本邦の外科医における医療機器開発・医工連携への興味が急速に高まってきていることを実感しています。その中で、外科医発の素晴らしい製品開発事例や開発の取り組みを目にする機会も増えてきています。一方で、機器開発が進み、製品として市場で販売していく過程(製造・販売路の確保、PMDA承認、販売実績・収益etc.)にも様々な困難があります。 In organizing this series since 2021, we have realized that interest in medical device innovation and medical-engineering collaboration among Japanese surgeons has grown rapidly in recent years. |
パネルディスカッション |
JSES-JSCASジョイントセッション 医療従事者の働き方改革を推進する医療DX ~わたしはこれで定時に帰ります~セッション趣旨はこちら 医療現場での長時間労働が常態化するなか、働き方改革には医工連携による医療DXの活用が不可欠である。AIやロボティクス、データ解析技術の進歩により、診療・手術支援や業務効率化が進み、現場の負担軽減が期待される。本プログラムでは、医工連携による技術が医療従事者の働き方をどう変革し得るかを議論し、現場の課題に即した革新的なソリューションを共有することで、「定時に帰る」ことを現実とする道筋を探る場としたい。 As long working hours in the medical field become the norm, the use of medical DX through medical-engineering collaboration is essential to reform the way of working. Advances in AI, robotics, and data analysis technologies are expected to support medical treatment and surgery and improve work efficiency, thereby reducing the burden on the field. In this program, we would like to discuss how technology through medical-industrial collaboration can change the way medical professionals work, and share innovative solutions to on-site issues, to explore ways to make “going home on time” a reality. |
ワークショップ |
カールストルツ賞に関して
本賞は、内視鏡外科手術の発展のために、優れた研究成果を発表した会員を表彰し、奨励するために1999年から設けられた制度で、当該年度の学術集会で発表される動画を対象として選考されます。
受賞者には賞状が授与され、副賞として10万円が贈呈されます。
応募方法
本賞に応募を希望される会員の先生は、演題応募時にカールストルツ賞「応募する」にマークしてください。
募集対象
第38回日本内視鏡外科学会総会で動画を用いて発表される一般演題に限ります。
選考方法
総会会長が選考し、受賞者は3名以内となります。
抄録本文による一次選考、その後、動画による二次選考という段階を踏んでおります。
一次選考通過者には動画の提出などにつき9月中にE-mailでのご連絡を予定しております。選考を通過されなかった方にはご連絡をいたしませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
利益相反(COI)開示と倫理的手続きに関しての指針について
利益相反(COI)開示について
第38回日本内視鏡外科学会総会にて発表をされる方は、利益相反の状況について、演題登録画面で登録していただきます。(※必須となります)
詳しくは以下リンクをご参照ください。(日本内視鏡外科学会HPリンク)
なお、上記の選択は演題採否には関係いたしません。
倫理的手続きに関しての指針について
学術集会へ演題を応募する際には「日本内視鏡外科学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」を遵守する義務があります。倫理審査が不要な研究以外は、演題登録時に倫理委員会の承認を得ていなければ、演題をご登録いただけませんので、十分にご注意ください。
演題登録
以下の「演題登録はこちら」ボタンから演題登録画面にお進みください。
非会員(現時点で筆頭演者が会員でない方、メディカルスタッフ・工学系研究者・初期研修医)
筆頭演者ならびに共同演者は全て会員に限りますので、未入会の場合は演題登録後、必ず入会申込を行ってください。
(メディカルスタッフ・工学系研究者・初期研修医・外国籍の方を除く)
会員情報に関するお問い合わせ
日本内視鏡外科学会 事務局
info-jses@convention.co.jp
演題採否について
演題採否は、E-mailでのご連絡および、本ホームページでご確認いただけるよう予定しております。採否公開時期につきましては、9月下旬を予定しております。
演題登録に関するお問い合わせ
第38回日本内視鏡外科学会総会 演題担当
E-mail:endai-jses38@convention.co.jp
入会や会員番号のお問い合わせ
日本内視鏡外科学会 事務局
E-mail:info-jses@convention.co.jp
会員番号やパスワードのお問い合わせにつきましては順次ご対応いたしますが、
大変混み合う可能性がございますので、お時間に余裕をもってお問い合わせください。